Mizuzu ネオは自身の障がいにとらわれることなく、常に新しい挑戦を続けるVTuberだ。
By Andrew Amos (2023/2/20)

Mizuzu ネオは、自分がふつうに言葉を話せたころのことを覚えていない。
23歳の彼女は、非常に幼いころに負った怪我のせいで物理的に声を出すことができなくなり、それからずっと自分を表現する方法を見つけることに人生を費やしてきた。
「声を出すってどういうことなのか、どうやったら声を出せるようになるのか、それを身につける機会は私にはほとんどありませんでした」と彼女は語る。
「声を出せることが人生において必要不可欠なことだと知るまでは、たいして影響がなかったんです。そう、『どうして私はお父さんやお母さんみたいに話せないの?』と思うようになるまではね」。
最初に取り組んだのは「伝える」ことだった。彼女はできるだけ早く文字を書くことを覚え、会話に参加するためにホワイトボードを持ち歩いた。
アニメファンなら『聲の形』の西宮硝子を思い浮かべるかもしれないが、Mizuzuにとってそれは映画ではなく現実だった。
幼少期の彼女はASL(American Sign Language、アメリカ手話)の個人レッスンを受け、手話を学ぶことに重きを置いていた。手話のレッスンには彼女の家族も参加した。相手が手話を知らなければ会話は制限されるが、それでも筆談よりはスムーズだった。
「『なぜ全部書かないのか』と聞かれたことがあります。でも、子どもにとってそれはとても難しいんです。話したい瞬間に書くのは本当に大変だから」。
言葉で感情を表せないとき、彼女はアートに救いを求めた。自称「日本のアニメ・漫画オタク」だった彼女は10代の頃にアートスクールに通ったが、弟が自分を超えるほど上達したことがショックで中退した(本当にそれが理由かは議論の余地あり)。
「当時の私は『アートは自分を表現する方法だ!』と思っていたんです。言葉で表現できなくても、文章や絵で表現できるんだって」。
そんな中でも、ゲームとオンラインカルチャーへの興味はずっと変わらなかった。PointCrowやAlpharad、Smallantといったゲーム配信者に夢中になり、自身もゲームに挑戦し、自分のスキルを限界まで高めていった。
声を出せない人間が映像コンテンツ制作者になる、ましてや配信者になるというのは前代未聞のことだった。しかし、Mizuzuはこれを挑戦と捉えた。
「どうして始める勇気が出せたのか、正直わかりません。だって、始めたときは『コミュニケーションの手段が必要だ』ということしかわかっていなかったから。かなり時間がかかったけど、なぜか自信と勢いに乗っていました。
最初はメモ帳を開いて、画面共有してドーン! という感じでした」。
陳腐に聞こえるかもしれないが、、VTuber活動(VTubing)は彼女に「失われた声」を与えた。これまで乗り越えてきた苦難? その苦難があったからこそ、もっと頑張ろうと思えたし、どうしたら上手くいくかという工夫もできたのだ。
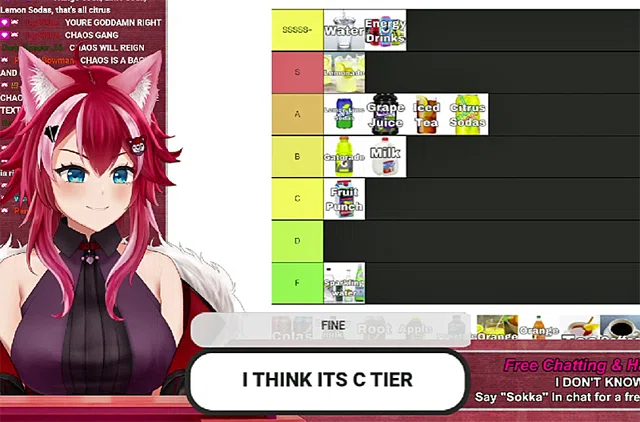
VTuber活動に光明を見つけた瞬間
Twitchで見るMizuzu ネオは、リアルとそれほど変わらない。彼女は配信外でもハイテンションで、純粋にカオスを楽しむ性格だ。彼女の配信は演技ではないのだ。
彼女には特別なキャラ設定(lore)はない。将来的にストーリーを作る可能性は否定していないが、今のMizuzu ネオは「現実の自分にちょっとした悪戯心とタヌキの姿を加えたもの」だ。
「配信でやっていることの半分はリアルでの私と同じで、キャラ設定を作るなんてことはできないと思います」と彼女は笑う。
「多くのVTuberがやっている、『キャラクターと“中の人”のギャップ』も私にとってはどうでもよくて、自分のことを好き勝手に話しているだけなんです」。
彼女がVTuberを始めたきっかけは、他の多くの人とそれほど変わらない。彼女は数人のYouTuberに影響を受け、そこからVTuberという沼にハマっていった。
しかし、彼女がデビューしたのはホロライブEnglishの登場前、2020年初頭のこと。当時、英語圏にもっと広いコミュニティがあることを知らなかった。
「私はほとんど何も知らないままVTuberのコミュニティに入りました。ほぼ1年間、ほぼ一人でVTuberのことを調べて、そのやり方を学びました。基本的にすべて自分で苦労しながら学んだんです」。
その後、Hololive MythがデビューするころにはVTuber界の可能性をなんとなく感じてはいたが、彼女たちのデビューをきっかけに、Mizuzuは将来を真剣に考え始めた。
「2、3年前、本格的に始める前はホロライブ、特に森カリオペに夢中でした。彼女を見ていたら『自分にもできるかも?』と思うようになったんです。
私がカリオペから刺激を受けたのは、彼女が好きなように自分を表現しているところ。歌ったり、ゲームしたり、ホロライブのみんなとたくさんコラボしたり、いろいろなことをやっている。
自分も好きなように自分を表現して、何も考えずにただ趣味としてやっても受け入れてもらえるんだと気づきました。でも、そのときは声を出さない配信者なんておかしい、と思ったんです」。
そして彼女がいろいろと調べ始めてから3か月後、Mizuzuはゼントレヤ(Zentreya)に出会う。VShojoのスターはMizuzuと同じような方法でVTuber活動を始めていた。
無言ではないものの、ゼントレヤは自身の声を発したことがない。ゼントレヤは当初、画面上のテキストボックスで会話していた。その後、彼女はプライバシーを守りながら少しでも交流しやすくするために、音声合成技術(speech-to-text-to-speech technology)を導入したのだ。
理由は違ったものの、大枠の考え方はMizuzuが望んでいたものと同じだった。その瞬間、長く配信を続ける未来を実現するための無数のアイデアが一気に湧き上がった。
「話そうとするたびに、相手には私がリアルタイムで文字を打っている様子が見えていたんです。新しい文章を始めるたびに、前の文章をバックスペースで全部消してから打ち直していたところまでね」と彼女は振り返る。
ただ、そこにはどうしても越えられない壁があった。Mizuzuにはいきなり声を出して話し始めることなどできない。それは、できること・できないこと、作れるコンテンツの幅を大きく制限していた。
Mizuzuとゼントレヤを比較するのは簡単だが、両者はまったく違う境遇にあるのだ(かつての私を含め、初見の視聴者の多くは同じように見てしまうが)。
「ゼントレアのことは大好き。でも、私とゼントレアは同じじゃない。私が声を出せないのは自分ではどうしようもないことだから。比較されるのはあまり好きじゃない。だって、『彼女はZentreyaっぽい、でもそれだけ』って言われている気がするから」。

「私の配信は他の人とは違う、ユニークなものにしようと心がけてます! 他では見られないようなコンテンツとかね。でも、自然な流れで比べられることについては気にしていません。
ゼントレヤの影響は大きいと思います。彼女は素晴らしいコンテンツクリエイターで、とても大好きです。私が何をするにしても、彼女と比較されるのは当然です」。
言葉を話せないまま大人になることの難しさ
Mizuzu ネオは生まれつき話せなかったわけではない。だが、彼女が知っていることはそれだけ。普通の人にとっては当たり前にできる簡単なことも、彼女にとっては当たり前ではないのだ。
ホワイトボード(あるいは他のツールなど)を使うことで、コミュニケーションは容易になった。しかし、より困難だったのは、彼女の障がいに対する社会的障壁と誤解だった。
「言うまでもありませんが、幼いころはしゃべれないことをバカにされました。学校ではいじめのようなこともありました。
辛かったのは“声がない”ってことが、みんなの興味の的になってしまうことでした。声って、私にとってはすごく大切なものだったから。それを持てないって知るたびに、心が折れそうになりました。
それよりも、私と同じような道を歩んできた人がほとんどいなくて、自分ひとりしかいないことのほうが辛かったですね。人と話す、ショーを観る、歌を歌う。どこを見回しても“声”があるのに、私だけがそれを自分の意思で選ぶことができなかったんです。
誤解されることも多かったけど、それで人を責めたりはしません。逆の立場だったら、きっと私もたくさん質問していたと思うから。
ときには私が耳が聞こえないと思われたり、本当に何か問題があるんじゃないかと思われたりもしました。『息はできる?』なんて馬鹿げた質問もされました。あれは一生忘れないと思います」。
「でもVtuber活動を始めたら、驚くほど多くの人が受け入れてくれたんです」とMizuzuは振り返る。ゲームやアニメに囲まれて育った彼女は、配信を始めるまで、ソーシャルメディアもあまり利用したことがなかったという。
Mizuzuが今まで体験してきた嫌がらせや閉鎖的な雰囲気はなく、リアルだと生じる障壁も感じずに交流できる機会がたくさんあった。チャットで会話をしていれば、周りは彼女が話せないことはあまり気にならなかったのだ。
「“受け入れられたい”と思ってネットに飛び込んだけど、最初からずっと超オープンな形で受け入れてもらえたのはとても衝撃的でした。
みんな信じられないほど私を理解してくれるけど、それがどうしてなのかもわかりません。多くの人が深い理解を示してくれることに、ただただビックリしているんです」。
I know that being a vtuber isn’t meant to be EASY as a mute and never said it was. I chose to do this because I wanted to, knowing full well.
— Mizuzu 💥🌸 (@MizunoNeo) March 3, 2022
I’ll keep kickin’ ass as your boss tanuki so leave it to me. I fkin love y’all and I’ll never stop doing my best. ✊♥️💓
(5/5) pic.twitter.com/xkvSIyfNk8
「幼いころ、両親は私がインターネットを使うことをとても警戒していました。それは大人になった今も私に影響を与えています。『ワンクリックですべての情報を盗まれるし、このカメラに姿を映したら住所も顔もバレちゃう!』ってね」。
終わりのない質問攻めや「どうして話さないの?」という言葉には、今でもイライラすることがある。
「TwitterやTikTok以外から来た人は、ほぼ必ず『なんで話さないの?』って聞くんです。だから、そのためのコマンドを用意してましたし、今でも使ってます」。
しかし、彼女が自分に言い聞かせていた重要なポイントが2つあった。ひとつは「声を出せないことが彼女を規定しているのではない」ということ。彼女が自分らしさを見せる方法は他にもあるし、声を出せないことが彼女の存在価値を決めるものではないということだ。
「(声を出せないことは)重要ではないと思っていて、それよりも自分自身と中身を大事にしています。。実際に行動することは、何かを“話す”ことよりも重要です。私を人間らしくしているのは間違いなく私の個性だし、それがなかったらきっと退屈な人間だったと思います」。
それを受け入れるのは難しいことだったが、彼女はこれまでもそうしてきたように、ことあるごとにそれに立ち向かい、解決策を見出してきた。
「あるとき決めたんです。『自分のやり方でやって、受け入れてくれる人に受け入れてもらえばいい』って。気にするのはやめて、声がなくてもできること、ほかにできることを考えるようになりました。そうしたら、『とにかく自分にできることでベストを尽くそう』という考え方になったんです。
私がワーカホリックなのもそれが理由だと思います。いつでも向上心を持って、より良いものを求めることに大きな意味を感じています。自分自身を受け入れ、自分ではどうにもできないことも受け入れ、すべてを自分のやり方でやろうと決めました! 好きなことをしたり、好きな服を着たり、そんな感じです」。
それでも、声があったらどんな人生になるか考えることはある。
「たぶん、配信で大声でみんなに叫ぶんじゃないかな。前にも考えたことがあります。もし私が話せたら、完全にヤバいやつになると思います。めちゃくちゃうるさくて、もうブレーキが壊れたみたいになる。
しゃべれるという高揚感で最初の半年くらいは超うるさくて、それからようやく落ち着く感じかな。もし話せたら自分をもっと表現できるだろうけど、そのとき自分が何をするかはまったく想像できないです」。
喋れないのにどうやって配信するのか?
Mizuzu ネオの場合、Twitchでただ「配信開始!」というわけにはいかない。話せないがゆえの制約もたくさんある。
まず、プレイに全神経を集中させなければならないゲームは基本的にアウトだ。Valorantや Apex Legendsなど、Twitchで人気のオンライン対戦ゲームのほとんどは除外されてしまう。タイピングに両手を使うため、実際にプレイする余裕がほとんどないからだ。
しかし、彼女はそれを完全に諦めはしなかった。本業で培ったプログラミング技術を生かし、Twitchのチャット欄にゲームプレイさせる仕組みを作り上げたのだ。「Twitch Plays Pokemon」(※)などに触発されたMizuzuは、ゲームを限界までカスタマイズし、独自の奇抜なチャレンジを行っている。
※Twitch Plays Pokemon:ゲームの『ポケモン』を、Twitchの配信チャット欄のコメントをコマンド代わりにしてプレイするというもの。初出は2014年とされている。
「Twitchのチャットで欄でどこまでゲームを動かせるか試してみたくて、思い切ってやってみました。。正直、自分の配信にコードを組み込むのは信じられないほど楽しいチャレンジでした。
私はいつも配信するとき、少なくとも何かしらのチャレンジをしてきました。Twitchのチャットユーザー同士がトーナメント形式で競い合うように強制したり、ランダマイザ―(ゲーム内のアイテム配置やイベント発生をランダム化するツール)ありでプレイしてみたり、罰ゲームありのプレイをしたり、ゲームを改造して難易度を上げたり。
プログラミングの要素を加えることでいろんなバリエーションが生まれて、とてもユニークになるんです!」
それをするためには配信外での仕込みも必要だ。ボタン操作のための複雑なコードを組むのは、ただ配信をするよりも負担は大きい。しかし、そのおかげでTwitchのチャット欄にゲームをプレイさせることができ、配信時間を「エンタメ」に費やすことができるのだ。
その最たる例が、格闘ゲームでのキー操作をチャットに割り当てた配信だ。Twitchのチャット欄と彼女自身が30秒ごとに操作を交代するというもので、その配信では毎試合苦戦するはめになった。Mizuzuはそれをいい意味で「大参事」と称した。
「その配信では、下ボタンのコマンドを『アヒル』(duck)と名付けたんです。なぜかというと、チャット欄(にコメントするファン)がそれを望んだからです。そこで、すべての移動コマンドをアヒルの形に変更しました。左に移動するときは『クワッ』(quack、アヒルの鳴き声)、右に移動するときは『マガモ』(mallard)といった感じに。
そしたらある人が、移動コマンドのひとつとして『危ないリッキー・ランブルのパパの変なガレージセール4(Risky Ricky Rumble’s Dad’s Weird Garage Sale 4)』という名前を提案したんです。そのせいで、コマンドを実行するたびにチャット欄にその長いコマンド名をフル入力しなければならなくなって。結局そのフレーズがどういう意味だったのか、いまだにわかりません。
その配信では4時間で1、2勝しましたが、4時間のうち2時間はコマンド名を決めるのに費やしました。正直、その配信の中ではそこが一番のお気に入りポイントです。今年はTwitchのチャットでランダムに話題を振りつつも、ちゃんとレールの上を進んでいくような、そんな形のコンテンツにシフトしていきたいですね」。
だからといって、Mizuzuがこの縛りを気に入っているわけではない。言葉を発せないがために、チャンスを得るよりもボツになったアイデアのほうが多いという。
「どんなに楽しい、すごいと思ったことでも、あきらめないといけないことがたくさんありました。音声操作や他の人とのコラボなど、声が出せないことがネックになります。話せないからという理由で、数え切れないほどのアイデアがボツになりました。
だから自分に合ったコンテンツを見つけるのはけっこう難しいし、Twitchのチャット欄にいるファンをどうやって楽しませたらいいか、頭をひねることになりました。特に私のTwitchのチャット欄にいるのは大勢のいたずら小僧のようなものなので。
ゲームに挑戦したり、Twitchのチャット欄を使ってゲームを操作したり、チャット欄のファン同士でトーナメント形式で競わせたりとか、より簡単にユニークなことができるスタイルに落ち着きました。こういうのが私にぴったりなんです!」
コラボはVTuberの間でも特に慎重になるポイントだ。Mizuzuは最近までテキスト読み上げソフトを一切使用していなかった(実際に使ってみたところ、視聴者が40%近く増えたそうだ)。
そのため、自分の配信に人を招待したり、他人の配信に出向いてコラボしようとするのはなかなかに大変なことだが、そのための工夫もしている。
Mizuzuはコラボ相手にはDiscordで自分の手打ちコメントを送る方法を取り、たいていの場合はゲームコラボをするなど、難易度の低い配信内容にとどめている。テキスト読み上げソフトを使えば楽になるだろうが、それでも限界はある。
「『エルデンリング』の全編ランダマイザープレイを通じて、読み上げソフトを力技で学ぶことにしたんです。ゲームをクリアするまでに、毎回およそ8時間の配信で7回かかりました。ちょっと違和感は残るけど、自分の配信スタイルにフィットする音声読み上げソフトもその中で見つけました」。
「アプローチがまったく変わるだけでなく、変な要素も加わっています! ソフトは私がメッセージを送ってから2秒くらい遅れて読み上げるんです。アバターには多少口パクをさせるんですが、ズレの穴埋めはほぼ私がやらなくちゃいけなくて、単語によっては口をどう動かせばいいのか全くわからないので大変です。
(反響は)とてもポジティブでした! コメント欄に書き込んだり画面をずっと見ていたりしなくても配信が楽しめるので、みんな信じられないほど喜んでいます」。
Mizuzu ネオの未来
配信が好きでなかったら、Mizuzu ネオはここまで来ることはなかっただろう。このメディアのおかげで、数年前までは想像もできなかったような自己表現ができるようになった。配信はまた、かつて得られなかった「ちゃんとした交流」をようやく手にできるようにしてくれた強力なツールでもある。
「配信の一番すごいところは、自由なコンテンツ作りができるところだと思います。本当に何でもできちゃうんです! 私はすごくクリエイティブな人間で、書くことも、企画することも、新しいアイデアを考えることも大好きです。だから、そのすべてを配信という“箱”の中に詰め込めるのは、とても素晴らしいことだと思っています。
でも、それだけじゃありません。だって、私がこういうことをやろうと思えるのは、コミュニティの人たちが私のすることを楽しんでくれて、もっと見たいと思ってくれるからこそなんです。
配信するたびに自分の新しい一面を発見している気がします。例えばサルのネタでジョークを飛ばすとかね(笑)。そういう新しい発見や、自分の限界はどこにあるのか、自分がどう見られたいか、そういうことを学ぶ機会でもあるんです」。
彼女の創造性は、彼女が配信を始めたユニークな経歴からきている。声を出せないことが「不幸中の幸い」というわけではないが、結果として他の配信者と一線を画すことにもなっている。
「もし私が声を出せていたら、たぶん私だけのユニークなスタイルや雰囲気もなく、普通にValorantの配信をしていたでしょう。私はそれを“神の祝福”とは思いません、むしろ“ナーフ”です。きっと私があまりにもすごくてクールでセクシーなので、世界のほうが私をナーフしなきゃって思ったんでしょう!
今がどうあれ、もし私が普通に話せていたら、それは私ではありません。声を出せないことが祝福だとは思わないけど、そのおかげで自分の道を切り開くことができたし、結果的にそれが創造性を高めて、私を特別な存在にしてくれたんです」。
I HAVE A FKIN AMAZING LOVING COMMUNITY. Thank y’all for being amazing 💞
— Mizuzu 💥🌸 (@MizunoNeo) February 16, 2023
You guys inspire me to work even harder. Fuck you!! 🫶 pic.twitter.com/SyqzyHJ3EA
彼女が歩み始めた頃と比べると、今のMizuzu ネオは「まったく別人」だ。それは彼女にとって、とても良い変化だった。
「今が人生で一番幸せです。『どうやってこうなったんだっけ? 最初からそうだったっけ?』ってね。VTuberとしての活動を始めた瞬間から、人生でこれほど幸せだったことはありません。ずっと上り坂でした。
ストレスが溜まる瞬間もあるし、気分の浮き沈みもあるけれど、配信を始める前の最低の状態とは比べものにならないです。配信活動を始める前は100点満点で最低値が1点、最高値は20点でした。今は最低でも50点、最高は1000点です」。
こうした創造への情熱とやりがいを求める気持ちが、Mizuzu ネオを3年目の大きな挑戦へと駆り立てている。2月20日にデビュー記念日を迎えた彼女は、次なる一年の幕開けに、大規模なサブアソン(subathon)を開催する予定だ。その先に何があるのか、それは誰にもわからない。
「これからも配信を続けてもっと大きくしていきたい! 大きなプロジェクトとか、多くのコミュニティに関連するものとか。それからコラボレーションもね。今までできなかったような大きなシリーズものやプロジェクトに力を入れたいです。
この一年は、キャラ設定や世界観みたいなものを作るとか、アバターのデザイン変更とか、ちょっとヤバいくらいクレイジーなことにも挑戦してみたいと思っています。今年はMizuzuの年だと決めているんです」。
Mizuzu ネオは、さまざまな魅力にあふれている。声を出せないことは彼女の物語や性格のほんの一部であり、決してそれだけが彼女を形作っているわけではない。彼女は騒々しくてとても競争心が強い、自称「グレムリン」だ。技術的なスキルも非常に高く、自分の存在をアピールするためのやる気も旺盛だ。
しかし彼女が唯一認めないのは、「かわいい」という評価だ。
「私は全然かわいくなんかないです! それだけは最期まで言い続けます。配信するたびにチャットは“かわいい”って大騒ぎだし、コラボ相手やスポンサーからも言われるくらいだけど…もう最悪です、私、絶対にかわいくないのに!」
※記事中で使用している画像は訳者が独自に用意したもので、元記事とは異なる場合があります。この翻訳記事のサムネイル画像はMizuzu ネオのTwitter投稿画像から作成しました。


